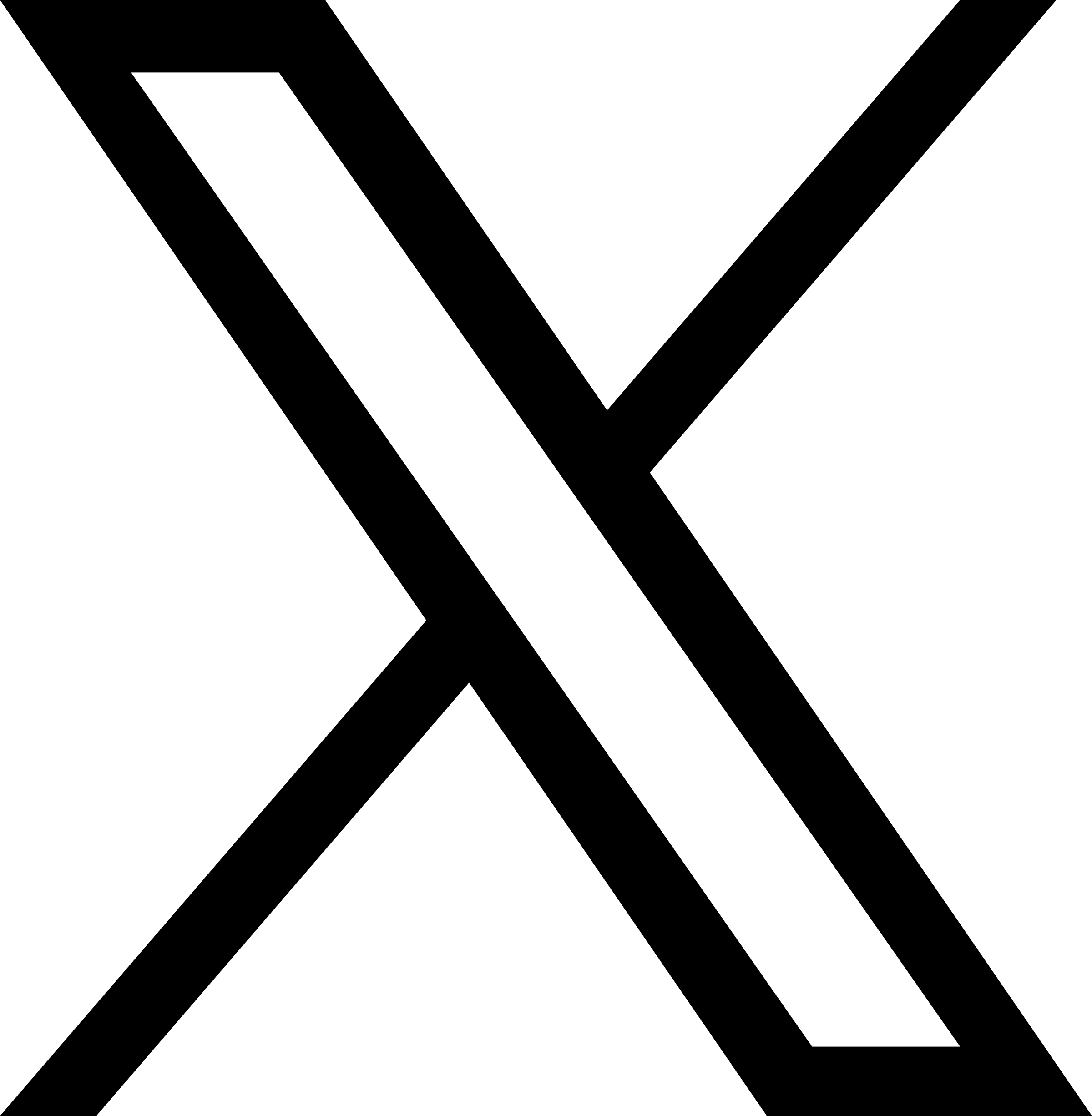連載記事ウェブアクセシビリティを知ろう
連載31:ウェブアクセシビリティ対応を始めてみよう
村上 桂子
2024年4月1日
ウェブサイトをアクセシブルなコンテンツにするために、よくある質問として
- 何から着手したらよいのか
- 何を実施したらよいのか
- 何を学べばよいのか
- 誰に相談したらよいのか
等がわからないという御意見が寄せられます。
一般的には、ウェブアクセシビリティ方針の策定をし、アクセシブルなウェブコンテンツに修正し、試験をする。そしてこのプロセスを繰り返し実施することが重要とされています。
しかしながらウェブアクセシビリティそのものを理解していないと、方針も立てられませんし、コンテンツも修正できません。また試験をする事はさらにハードルが高いですね。方針を立てるにしてもサイトをリニューアルするにしても先ずは現状のサイトを検証することが重要だと考えます。今サイトが於かれている状況を把握しないことには先に進みません。では、検証するためにはどのような知識が必要なのでしょうか。
日本では、試験をする手段として、JIS X 8341-3が使われることが使われることがほとんどです。
また検証もJIS X 8341-3に基づいて実施します。
このことからまずは、JIS X 8341-3を理解することが重要です。外部の機関に検証だけを依頼することや機械チェックで確認する方法もありますが、それぞれメリットデメリットがあります。
外部の機関の場合、デメリットとしては料金がかかることと、機関によって検証内容が変わります。メリットとしては専門的な角度から検証してくれますので、はじめの一歩としては有効ですね。検証内容が変わるとはどういう意味かと申し上げますと、そもそもJIS X 8341-3に基づいて検証を実施しているなら機関によって結果が変わるはずはないと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、実際に複数人で検証してみますと、人によってJISの解釈が異なり結果が違ってくることがあるのです。次に機械チェックで確認すると、デメリットは、目視でしか得られない結果が見えてこないこと事です。メリットとしては、コストをかけずに一部の結果を除くおおよその判断が出来ることです。2024年に障害者差別解消が改正されました。よりウェブアクセシビリティ対応したサイトが求められるようになってきます。
是非今年はウェブアクセシビリティ対応の一歩を踏み出してみませんか。