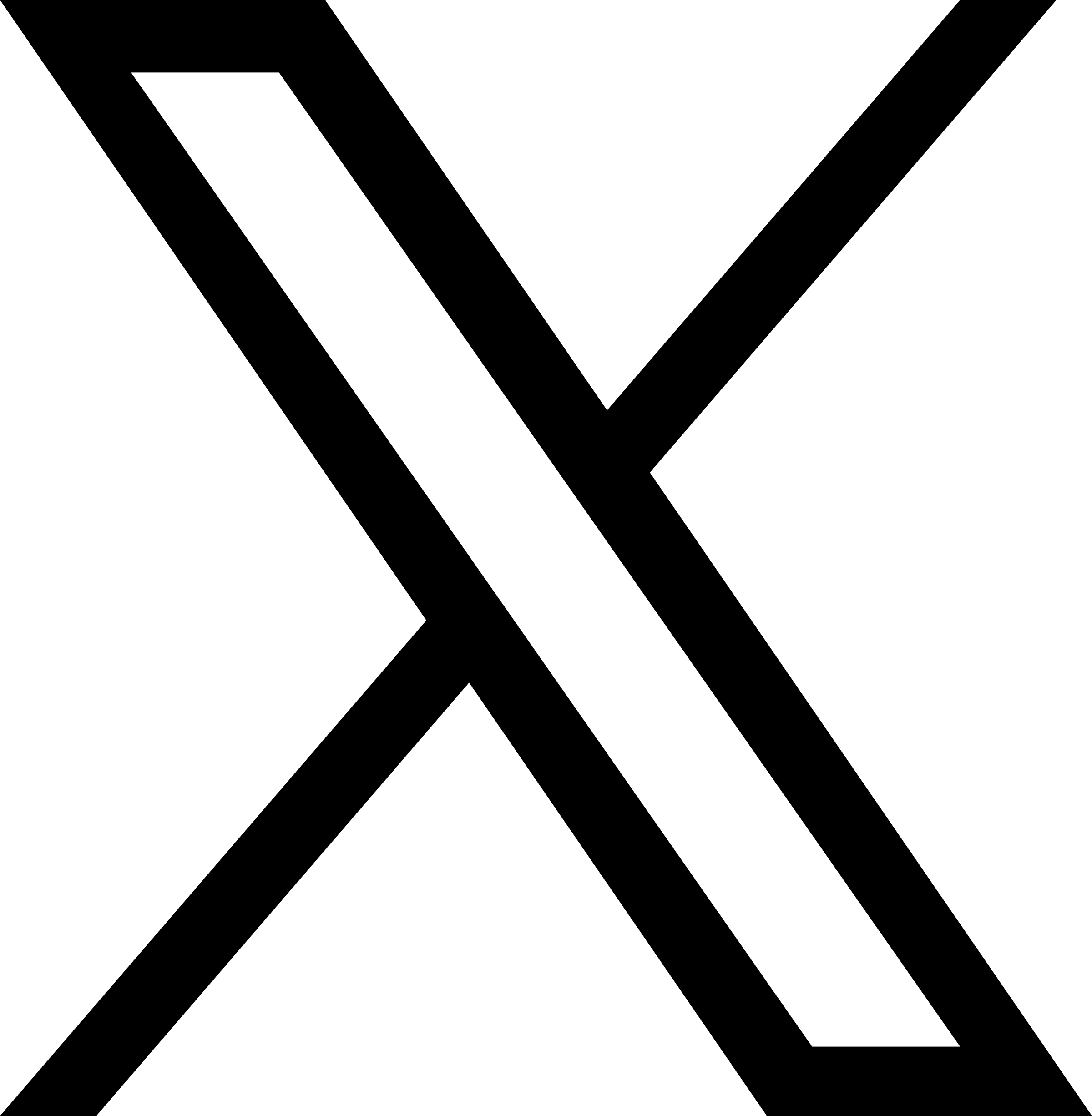連載記事多様なユーザーのための「アクセシビリティ」入門
連載32:多様なユーザーのための「アクセシビリティ」入門
渡辺 隆行(JWAC理事長,東京女子大学)
2025年3月31日
久しぶりの連載記事執筆となりましたが,今回は基本に戻って,2025年2月25日に株式会社Cradle![]() の会員向け有料セミナーでお話ししたアクセシビリティ入門者向けのお話のスライドを,JWACのサイトをご覧になっている皆様と共有したいと思います.
の会員向け有料セミナーでお話ししたアクセシビリティ入門者向けのお話のスライドを,JWACのサイトをご覧になっている皆様と共有したいと思います.
詳しくはスライドをご覧になっていただきたいのですが,渡辺がこのセミナーでお話ししたかったことを簡単に振り返ります.
なぜアクセシビリティに配慮する必要があるのか?
それは,多様な人々が暮らしているからです.ユーザ(Webを使う利用者)というと特別な配慮を必要としない健康な成年男子を思い浮かべることが多いと思いますが,感覚機能に配慮すべきユーザもいれば運動機能に配慮すべきユーザもいれば認知機能に配慮すべきユーザもいます.これらの方々はマイノリティなのでマジョリティ中心の世界では注意を払ってもらえないことが少なくありません.でも,全ての人に基本的人権があり,誰もが勉強したり働いたり遊んだりなど,自分の人生を幸せに生きる権利があります.その権利を守る必要があります.他者の生活を想像できないあるいは知らないと,ステレオタイプが生まれたり偏見や差別が生じたりします.ですから,いろいろな人々の生活を想像したり理解したりする能力が必要だと思います.
米国でDEIが話題になっているのでこの言葉を聞いたことがある方も多いと思います.DEIとは,Diversity(多様性),Equity(公平性),Inclusion(包括性)の頭文字ですが,ここではアクセシビリティも含めてDEI+Aと考えたいと思います.多様性は先ほど述べた多様なユーザの存在を認めることです.よく誤解されるのが公平性(Equity)で,平等性(Equality)とは異なる概念です.背の高さにかかわらず全員に同じ高さの踏み台を配るのは平等で,背が低い人には高い踏み台を配って壁の向こう側を見えるように配慮するのが公平です.全ての人に同じ機会を提供する平等と,個人のニーズや特性に合わせてサポートを調整して結果として平等になるように配慮する公平は異なる概念です.このサポートは,障害者差別解消法のキーワードである合理的配慮とつながります.
ICFのモデルでも障害学でも「障害は社会の中で生まれる」社会モデルが主張されています.個人の身体的機能のimpairmentと社会制度に起因する障害(disability)を明確に区別しています.障害者とは,「社会的障害物によって能力を発揮する機会を奪われた人々」であると捉えて,障害者差別解消法などの強制力を持って障害を除去することを目指しています(杉野:『障害学−理論形成と射程』東京大学出版会).
障害者差別解消法は皆様もよくご存じだと思います.2024年4月に合理的配慮の提供が民間でも義務になったことで話題になりました.先に説明した「公平(Equity)」という概念を持っていると,合理的配慮を理解しやすいと思います.
アクセシビリティとは何?
スライドの後半では,アクセシビリティの定義をユーザビリティと関連付けて説明しました.ユニバーサルデザイン,バリアフリー,インクルーシブデザインとの違いも説明しました.詳細はスライドをご覧ください.
まとめ
WebサイトがJIS X 8341-3の達成基準を満たしているか,テストに合格したかという前に,Webのアクセシビリティとは何なのかをもう一度考える必要があると思います.多様な特性とニーズを持つユーザが利用できるようにWebを制作するという視点があってはじめて,Webアクセシビリティの理解が進んでいくと思うのです.