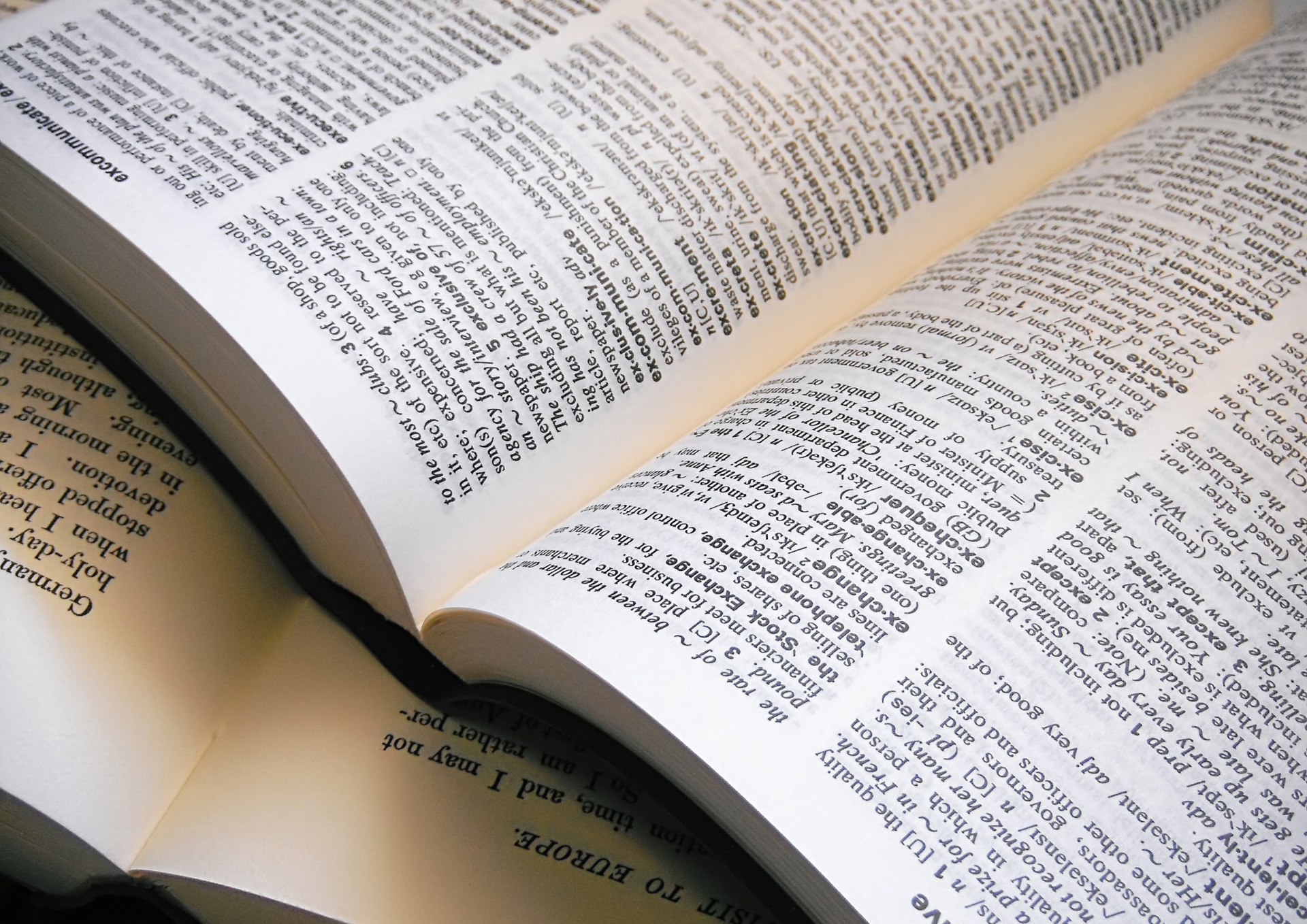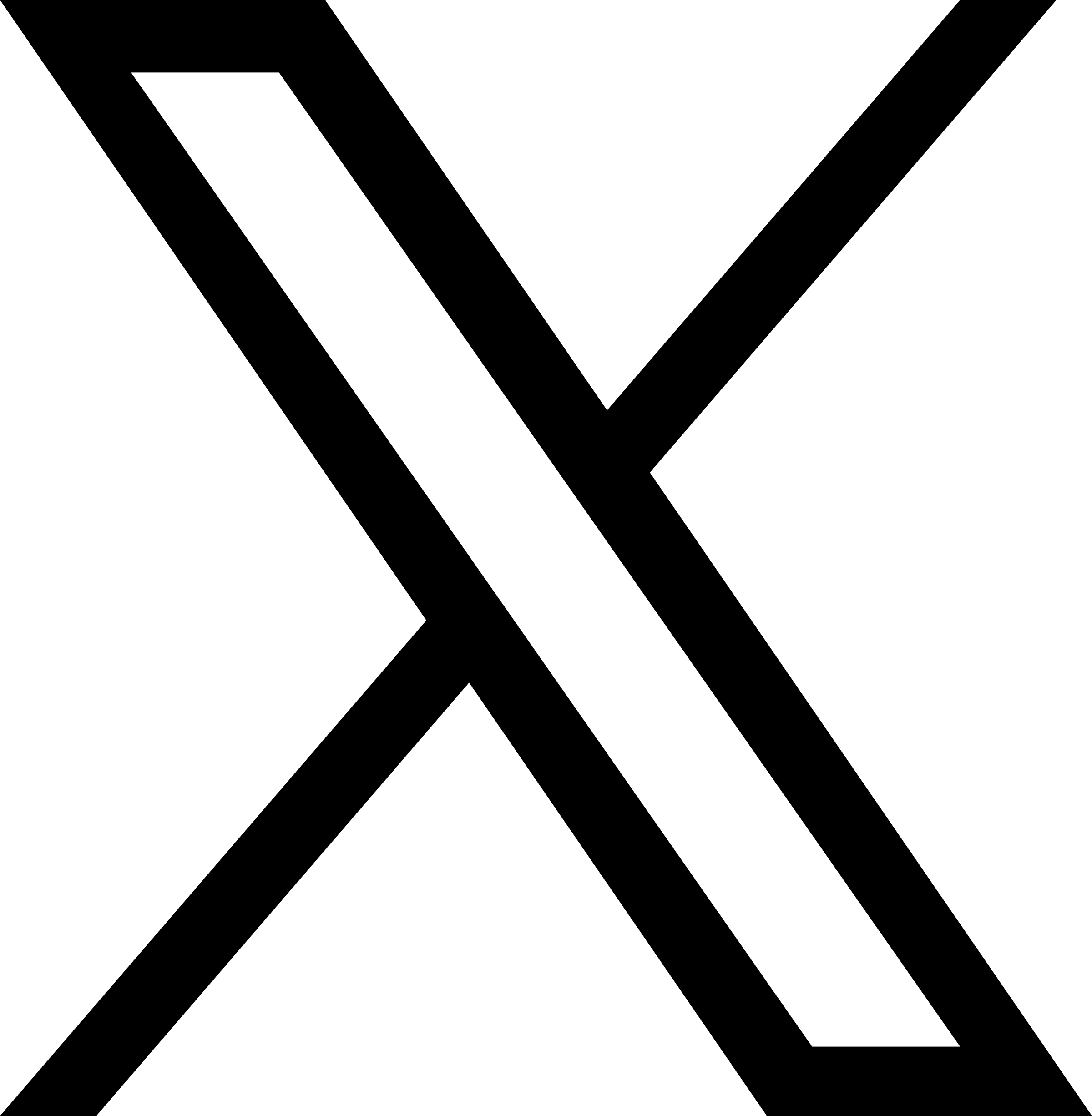連載記事ウェブアクセシビリティを知ろう
連載22:ウェブアクセシビリティとADAに関する手引き(その2)
山田 肇
2022年3月25日
(手引き本文)
ウェブアクセシビリティに関わる障壁の事例
色のコントラストが悪い
視力が限られている人や色覚異常の人は、テキストと背景のコントラストが十分でない場合(たとえば、明るい色の背景に明るい灰色のテキストといった場合)、テキストを読めない。
色だけで情報を提供する
色覚異常の人は、特定の色を他の色と区別できないため、色の手がかりだけを使用して情報が伝達されると、情報にアクセスできない場合がある。また、スクリーンリーダは画面上のテキストの色をユーザに通知しないため、目の不自由な人は、色が特定の情報を伝えるために付けられていると知ることができない(たとえば、入力フォームの必須項目を赤色のテキストだけで表示する)。
画像に代替テキストがない
目の見えない人は、代替テキストが提供されていない場合、写真、イラスト、チャートなどの画像の内容と目的を理解できない。代替テキストは写真、イラスト、チャートなど、画像の目的を伝えるものである。
動画にキャプション(字幕表示)がない
動画にキャプションがない場合、聴覚障害のある人は動画で伝えられる情報を理解できない恐れがある。
アクセスできないオンラインフォーム
障害のある人は、情報に以下のようなものがないと、フォームに記入、理解、および正確に送信できない場合がある。
- 「クレジットカード番号」を入力する場所に「クレジットカード番号」というテキストを添えるなど、スクリーンリーダからユーザに伝えられる表示
- 明確な指示
- エラーインジケータ(入力項目の記入が欠落している、あるいは正しくないとユーザに通知するアラートなど)
マウスのみのナビゲーション(キーボードナビゲーションの欠如)
マウスやトラックパッドを使用できない障害者は、キーボードを使用してウェブサイトをナビゲートできない場合、ウェブコンテンツにアクセスできない。
(解説)
手引きはウェブサイトの障壁の具体的な説明からスタートしている。手引きの後半には、ここで提示した問題への解決策も説明されている。基礎から、ウェブアクセシビリティについて説明しようという姿勢がうかがえる。
代替テキストの説明で、画像だけでは視覚障害者は「内容」と「目的」を理解できないとしたうえで、代替テキストは画像の「目的」を伝えるものであると説明している。代替テキストによる対応には限界があるので注意するべきである。